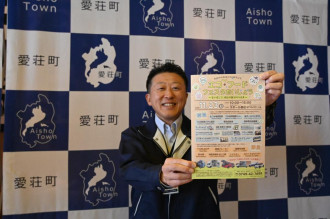暮らす・働く
多賀大社で「節分祭」 年男年女107人が奉仕、鬼の舞も

多賀大社(多賀町多賀)の「節分祭」が2月2日に行われ、境内は福を求める大勢の参拝者たちでにぎわった。
[広告]
古来、飢餓や災害などは鬼の仕業だと考えられ、奈良時代に大はやりした疫病をはらうために宮中で行われたのが節分の始まりとされる。江戸時代になると社寺や民衆の間にも広まった。
多賀大社での節分祭は1952(昭和27)年から執り行われている。毎年、県内外の還暦の男女が、境内に設けられた特設舞台から福豆と福餅をまき、今年は午前の部に55人(うち女性14人)、午後の部に52人(うち女性11人)が参加した。
男性が裃(かみしも)、女性が千早(ちはや)姿となり、全員が赤頭巾をかぶって奉仕。本殿での祭典に出席した後、特設舞台の上に移動。舞台上では島根県の因原神楽団による「鬼の舞」が奉納され、鬼の面をかぶった演者たちが舞を披露した。
その後、多賀大社宮司らが矢を放つのを合図に始まり、巫女(みこ)の「鬼は外、福は内」のかけ声に合わせて、年男と年女が福豆と福餅をまくと、参拝者らがわれ先にと手を伸ばしていた。福豆の中には「当たり豆」も入っており、当選者には景品が進呈された。
午前と午後で福豆1万袋と福餅約50キロがまかれた。